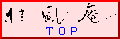
|
書道人の常識は一般の非常識? この講座の資料を作るにあたり、改めて文房具としての書道用具の名称あるいは用語について考えさせられた。 現代の書道離れの一因は、基本用語の説明から始まっているとも言えるのでは・・・ 一昔は何となくわかっていたことも、現代では馴染みのない用語であったり、難しく感じられることばであるがために興味関心を持ってもらえず、離れていくこともあるかもしれない。 指導者たるもの、きちんと把握してそれをわかりやすく説明ができるだけの技量を!!(反省ッ!!) |
|
「楷書と行書どちらが先にできた?」「書体は何故変わっていったのか?」「篆書や隷書が筆で書かれるようになったのはいつの時代から?」と、塩出の講義は人を混乱させるようなことばかり。 でも、これは結構重要なことだと思うんです。伝達するための文字は伝達相手や伝達理由によって書体を変えてゆきました。そして、また芸術としての書表現の多様性が、太古の文字を大字化させています。 日ごろの習字教室や書壇での様々な作品制作の背景には文字の持つ表現性が伝達性を超越したことがあるわけですねえ。 これからは、何のために書道教室が存在するのか、書道展があるのかをきちんと説明できないと、書道人が増えないのではないかしら、と思います。 教養、たしなみとして書道を習う人は減るでしょうから、もっと積極的な目標を掲げなくては!!書道が生き残るのは、なかなか大変です。 |
|
広島市内袋町という場所に、「頼山陽史跡資料館」がある。ここには、江戸時代の儒学者であった頼家の資料が収蔵、展示されている。 町の真ん中にあるにもかかわらず閑静な佇まい。収蔵庫、展示室、そして頼山陽の居室が復元されている。頼山陽という人物は『日本外史』を執筆した人物として有名であったが、それも段々と地元では知る人が減っているのがざんねんである。 学者の一族であるから当然文字は上手い。頼山陽と交流のあった市河米庵は書家とし有名であるが、その米庵が山陽の書を絶賛したという。 山陽の書を時系列で列挙すると、彼の書の技量がよくわかる。また、書風の変遷と彼の生活を重ねることで、書にはやはり人の生き方が出るなあとかんじることができる。 しかしまあ、残す努力をしないと、このように大量の書は残らないわけで、やはり文字というものを大切にする学者の家ならではの出来事(他にことばが見つからない) 残すべく努力をした人のものが残るわけで、生きることに執着心のない者のものは絶対にのこらないんだな、と実感。歴史は執着心によってつくられる。 |
|
「宮島、厳島どちらが正式名称?」「(厳島)神社になぜ、仏さまのお経を奉納したの?」と、塩出の講義は例によって、脱線ばかり。でも、“知っているようで知らない地元の話”ともいえます。 「平清盛は白河天皇の落胤だから、出世して太政大臣になったけれど、同じ年に生まれた西行は上流貴族にはなれないから出家してしまった。」というこの時代。いつも時代も権力者が正義。まあ、この清盛の名誉欲がなければ、宮島は観光地としての今はないわけですから、良いことをしてくれたのです。 他に類が少ない絢爛豪華な『平家納経』。平安時代の広島は京都からみればものすごいイナカ、よくぞこんなものを…と思ううけれど、当時の京都ではこのような物を制作する貴族の文化はあったわけで、『西本願寺三十六人歌集』と『平家納経』は同時代。朝廷や上流貴族より財力のあった清盛なら可能であったわけです。 厳島神社所蔵国宝『平家納経』は、他県の美術館で展示されると入館率がよいという。この国宝、毎年展示公開されるのに、地元広島県民は関心が薄い。しかも、「国宝展示中」という入り口のポスターに惹かれ、宝物収蔵庫に入った人は、入場料(1000円)が高いと文句を言う。薄暗く、狭い収蔵庫の展示など10分もあれば見終えてしまうからである。しかし、800年以上昔のものは、修復にも相当な費用がかかるのだから、維持費用カンパとして協力するべきでは・・・ この『平家納経』の複製も厳島神社にあるのだが、これが、平安当時のきらびやかさを再現していて、本物より豪華である。回廊を通り抜けてた先にある、宝物館に常時展示してあるのだが、これを本物と勘違いする人は多い。 本日の受講生さんがた、どのくらい『平家納経』に予備知識があったのでしょう。 「田中親美」への関心も高いようでしたが。 文化講座は、なかなか大変です。 |
|
「顔真卿の書って知っている?」ときかれると、書道を長くやっている人なら「ああ、あれね。」と、いくつかの書は思い浮かぶ 『顔氏家廟碑』、『麻姑仙壇記』、『多宝塔碑』、『顔勤礼碑』、『争座位帖』、『祭姪文稿』など、碑文の文字も手紙の草稿もある。 これらの文字は臨書され「顔法」という筆法が伝えられ、「顔真卿風」の書が後世に輩出されている。 碑文の文字は拓本として伝世してゆくのだが、その過程での評価が書論としてこれも伝世している。学者先生は、これらの研究あるいは、これらによってさらに研究をされるが、一般人にはあまりその情報はもたらされない。というか、わかりやすく話をしてもらえるチャンスがない。 この講座ではそのほとんどないチャンスを得て、わかりやすく話を聞くことができる。 石は壊されて消滅しても、拓本が残っていればさまざまなことがわかるようだ。原石は一つでも、拓本を調製した時代が違うと、その間の変化から背景が見える。まさに、「拓本は語る」である。 「八関斎会報徳記」「東方朔画賛碑」「蚕頭燕尾」「顔魯公祠」など、何となく聞いたことのあることばについておもしろく、またわかりやすくお話くださった、とのこと。ヤボ用で欠席したことが悔やまれる。 |
|
昨年12月から文房四宝についての話が続いた。 印の話、紙の話、そして筆の話・・・どれもこれも、「目から鱗」であったと思う。 長い間、書道と称して文字を書いていると、文具についても漠然とした知識の蓄積はできる。しかし、その中には単なる思いこみや、商売上の業者の言い分、思い違いなども含まれる。 今日、筆・紙・墨・硯は単に用具・用材としてしかの扱われていない。まあ、選ぶ基準としては、書きやすいこと、展覧会の規定のサイズであること。師匠の推奨品であるもの。そんなことが基準である。そう、あとはリーズナブルなもの・・・ 「文房四宝」という扱いはない。 しかし、これらは書道史のなかでは「宝」として愛でられた時代があるのだ。展覧会至上主義の現代では、そんなことはとうに忘れ去っている。 筆についての講座では、「筆は蒙恬が作った」と言われているが、伝承に過ぎない。という話から始まり、最古の筆の形状は、先生お手製の複製の筆でイメージは、よりくっきり。 紙と筆の関係も必然であることに、一同「な~るほど」 羊毛は羊の毛ではなく、山羊の毛。それも、本来は食べるために飼われるのであって筆の毛を採るためではないから、3年ほど成長した山羊の毛しかとれないそうです(それ以上成長させては食肉の価値がさがるため)「じゃあ、良い筆を作るためには、山羊を飼わなきゃ」という誰かの声で、大笑い。 それぞれの講師の視線で用具・用材の話を聞くと、知識が広がる。 こんな話を聞いたあとでは、紙や筆を見る目が変わるだけではなく、作品を見る目も変わります。 歴史的な観点、実物の提供、耳から、目から・・・お得な講座である。 う~ん 満足!m(^o^)m |