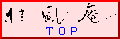
|
書道は書くだけのものではありません。美術や音楽のように鑑賞するに値する芸術です。けれども多くのひとが、「書道は読めない、何が書いてあるのかわからない。」あるいは「私は字が下手だから・・・」といって敬遠します。 美術や音楽は自分が描いたり、弾いたりしなくても鑑賞しますが書道は書けないからといって、鑑賞の方法までも見捨てられていませんか? ということで、大学で書道を担当する教師4人で始めたこの講座です。 過去の講義内容は以下のとおり。 |
|
【2010年 ♪新!♪講座内容および担当者】 書道鑑賞入門講座が5年も続き、入門というレベルではなくなりましたので、午後から新に入門講座を開講しました。こちらの講座は1年間で終了です。その後は研究科へどうぞ!! 10月30日 第1回 書と文房具 (担当者:宮崎(広島文教女子大学)) 11月27日 第2回 文字と書道(担当者:塩出(安田女子大学) 12月25日 第3回 書の基本用語(担当者:塩出) 1月22日 第4回 現代の書(担当者:塩出) 2月26日 第5回 楷書と行書(担当者:宮崎) 3月26日 第6回 行書と草書(担当者:宮崎) |
|
【2010年度 前期講座講義内容】
4月 書道鑑賞とは (塩出(安田女子大学)) 5月 唐代の書家について(日比野(広島文教女子大学)) 6月 書の頂点に立つ王羲之の書法とそれを享受した書家(日比野) 7月 江戸時代の文化と書。本阿弥光悦・池大雅など(森(広島文教女子大学)) 8月 書論1 唐代の書家について(宮崎(広島文教女子大学)) 9月 厳島神社所蔵国宝平家納経、その成立と美的な価値(塩出) 【後期:リニューアル『書道鑑賞』研究科 講義内容】 10月 *第5週 石碑と拓本のお話。(担当者:宮崎) 11月 頼山陽と市河米庵 (担当者:日比野) 1月 茶道と日本の書(古筆)について。(担当者:塩出) 2月 書論2 宋代の書家について。(担当者:宮崎) 3月 中国の現代の書 (担当者:宮崎) |
|
【2009年度講座内容】(2009年4月25日より開催) 4月 書道鑑賞とは (塩出) 5月 書の頂点に立つ王羲之の書法とその書法を享受した書家の話(日比野) 6月 書と絵画との関わり (森) 7月 おなじみの明朝活字。これは唐の時代に活躍した顔真卿の書(宮崎) 8月 宋代の書家の話。手書き文字にはその人の思想も現れます (日比野) 9月 石碑と拓本のお話。拓本にとられた文字の元の姿について (宮崎) 10月 古筆について *第5週に日時変更 (塩出) 11月 文房四宝 書の印について(宮崎) 12月はお休みです 1月 文房四宝 中国の紙 (宮崎) 2月 文房四宝 日本の紙(塩出) 3月 文房四宝 筆 (日比野) |
|
【2008年度講座内容】(2008年4月26日より開催) 2008年4月 文字の発生1 中国編 (日比野) 殷、周時代。甲骨に刻まれた文字、金属に鋳込まれた文字の発見と書体、書風 2008年5月 文字の発生2 日本編 (森) 飛鳥時代、奈良時代の文字。金属や石、木簡に書写された文字の発見と書体、書風 2008年6月 書体の形成1 中国編 (日比野) 木簡、石碑、布帛に書写された文字 2008年7月 書体の形成2 日本編 (塩出) 紙に書写された文字。漢字を中心に 2008年8月 書体の完成1 中国編 (宮崎) 王羲之の書から唐の四大書家の書 2008年9月 書体の完成2 日本編 (塩出) 平安時代から鎌倉時代のかな文字を中心に 2008年10月 書の鑑賞の発生 中国編 (日比野) 宋代における書の鑑賞 2008年11月 書の鑑賞の発生 日本編 (塩出) 茶席における書の鑑賞 12月はお休みです 2009年1月 書の実用と芸術 中国編 (宮崎) 明、清代の長条幅の書 2009年2月 書の実用と芸術 日本編 (森) 江戸時代における儒者の書、書家の書、貴族のの書 2009年3月 中国の現代の書 (宮崎) 日本では現代は日展を頂点とした展覧会が現代書を代表しますが、本場中国では? |
|
【2007年度講座内容】(2007年4月28日より開催) 4月 中国の書の鑑賞(1) かけあし中国書道史と拓本の魅力(宮崎) 題跋と鑑蔵印は歴代の鑑賞の足跡。それはどのようなもの、誰が作成したのか。 5月 中国の書の鑑賞(2) 手本となった拓本について(宮崎) 石に刻された文字を、拓本という形式で手本とした中国の文化の話 6月 中国の書の鑑賞(3) 拓本史料の変化(宮崎) 拓本から見る石碑の状態。後世の人々の修復 7月 日本の書の鑑賞(1) 古筆の現在-美術館所蔵の古筆-(塩出) 古筆(日本の古い書跡)はどのような経緯で美術館に所蔵されたのか 8月 日本の書の鑑賞(2) 芸術としての書の鑑賞(塩出) 日本では実用のためであった書道が、いつ頃から芸術作品となったのか 9月 中国の書と人物(1) 初唐の大書家 歐陽詢の人柄と書(日比野) 10月 中国の書と人物(2) 同じく初唐の大書家 褚遂良の人柄と書(日比野) 11月 中国の書と人物(3) 晩唐の大書家 柳公權の人柄と書(日比野) 「心正則筆正」ということばは良く耳にする。しかしそれがこの柳公權の名句ということを知る人は少ない 彼の書には暗さがなく実に大らかであるとか 12月 日本の書の鑑賞(3) 近代書壇の発生とその活動(塩出) 書道鑑賞の一方法は展覧会作品を見ること。書道展の発生時期とその後の話 2008年1月 日本の書の鑑賞(4) 「石山切」 |
|
2006年4月ー2007年3月 講座ダイジェスト 第1回 担当 宮崎・塩出 《かけあし書道史》 5月以降の講座に登場する人物・事項をキーワードに、文字の発生から現代までの歴史や、中国と日本の書の影響関係などをわかりやすくお話しました。 社会人対象の講義は初めてのこと。一体どんな方が受講されているのかと、塩出はビクビク。でも心配は要りませんでした。学生とは違って(笑)みなさんとても熱心に聞いてくださいました。 第2回 担当 日比野 《書の頂点に立つ王羲之(おうぎし)の書法とその書法を享受した書家のおはなし》 書聖とあがめられ、多くの追従者を輩出した王羲之。彼の書は今日もなお、書道の学習の基本として尊重されている。その書の魅力と価値についてのおはなしでした。 日比野先生は、毎年、学校で社会人対象の書道講座をされています。 さすがに講話も巧み。みなさん興味津々。お話しに引き込まれていましたね。 第3回 担当 日比野 《誰もが知っている明朝活字。これは唐の時代に活躍した顔真卿の書がモデルです。》 王羲之に次いで人気の高い顔真卿(がんしんけい)。彼もまた多くのエピソードを持つ魅力的な人物。王羲之のが伝統であるならば、彼の書は革新。顔真卿に心醉した後世の書家も数知れず。書道史においてどのようなキーパーソンであったかというお話しでした。 今回は実技付きでした。顔真卿の特徴のある字を日比野先生の解釈で書いてくださいました。ナルホド、ナルホド・・・ 中国の歴史の好きな人にはとても面白い話だったと思います。 実技付きの講話なんて、お得感ありますね(笑) 第4回 担当 塩出 《平安時代のかな書の尊重》 見事な筆跡で書かれ、美しく仕立てられた歌集は、平安貴族の姫さまのお輿入れの必需品。この歌集は、三大嫁入り道具の一つ。しかも、馬や琴より尊重されたとか。今で言うならば、ロールスロイスやグランドピアノよりも、「○○大先生のお書きになった俵満智さんの歌集」のほうが上等!ということです。いったい、どんな歌集が、どのようにもてはやされたのでしょうか? 現在放映中のNHK大河ドラマ「功名が辻」の中心人物山内一豊の家に伝来のお宝「高野切(こうやぎれ)」は、古美術商の評価では7億から十数億円と評価された。なぜ古筆はこんなにも高い値が付くのか、というお話し。 塩出の話は格調がないかな~? でも、古筆は本来、仮名の作品の手本ではなく、美術品であることを知ってもらいたくて・・・ 第5回 担当 塩出 《絵巻物の成立と享受 -源氏物語絵巻と佐竹本三十六歌仙絵巻-》 昨今テレビでも話題になった源氏物語絵巻。制作当時の色づかいはずいぶんと華やかだったようですね。絵巻物が多く作られていた時代には、その言葉が書かれた料紙もキラキラ華やか。こんな絵巻物の制作を命じた人物はさぞかしリッチなお方。誰が誰に何のために作らせたのでしょう。そして、それらはどうして現在のような形になって伝えられているのでしょうか。 第6回 担当 森 《江戸時代の文化と書。書の美はどのようにして受けつがれていったか》 天下取り合戦にあけくれる武士達の憧れは王朝の雅。室町以降、戦禍によって、多くのものが焼け失われましたが、美への憧れは焼きつくされることなく伝えられました。茶道や和歌・俳句の隆盛に伴い、書もまた独特の展開をしました。江戸時代の美の世界にタイムトラベルして、書の美がどのように受けつがれたかを垣間見ましょう。 第7回 担当 森 《明治時代の書 文人・芸術家の書》 明治時代になると書を専門の職業とする書家が現れます。その一方で、政治家や学者などの文人的な書も多彩な表現があり見逃せません。書が歌や文を記録するものではなく芸術として認められるようになった、つまり、実用の美が芸術美へと変化したのが明治時代なのです。 第8回 担当 森 《現代日本の書 書と絵画との関わり》 昭和20年代の後半頃から、書道はさらに、さまざまな表現の作品が現れます。絵画のように壁面で鑑賞されるようになり、文字の芸術というより、白と黒(時には赤や金)の織りなす空間芸術を創造した先駆者のおはなしをします。 第9回 担当 宮崎 《石碑と拓本》 書道教室に何年も通っていると、先生のお手本ではなく“法帖”というものをお手本として学習するようになります。白い紙に黒い墨で文字を書くのに、お手本は黒い紙に白い文字になるのです。それも、時には文字の一部が欠けていたり、輪郭がはっきりしていなかったり、黒い部分には白い斑点のようなものがある。最初は、こんなもののどこが良いのかと戸惑います。そのうちこの拓本の虜になって、これはどうやってできたのか、何のために作られたのかということも知らないままでおわってしまうのです。拓本の文字の元の姿についてお話します。 「石碑」「拓本」といった用語は書道では少し上級クラスで用いる語彙です。内容は少しハイレベルなことでしたが、でも先生の巧みな話術でみなさんお話しに引き込まれていました。 ある受講者曰く、「あっという間の90分でした!ちょっと偉くなった気になれました。」 第10回 担当 宮崎 《石碑自体の変化と後世の人々の修復》 中国のいにしえの人々は、石に彫られたものは永遠と信じ、後世に残すべく文字を石に刻み込みました。そして、できるだけ長く伝存するようにとさまざまな場所を選びました。永久であるはずの石碑も風化したり、破損してゆきます。また、後世の人の手によって修復という名目でその趣が変わってゆくこともあります。拓本に取られた文字からもその変化を窺い知ることができます。 第11回 担当 日比野 《手書き文字にはその人の思想も現れます。苦悩の書家、黄山谷の書の魅力》 文字は伝達という実生活での役目を果たすだけではありません。時にはその人の生きざまも見せてくれます。書は書かれた言葉よりも多くのメッセージを発信します。黄山谷がその書によって語りかけることを感じとってみましょう。 |
|
【ちょっとおもしろい話 ー知っているようで知らない「甲骨に刻まれた文字」ー】 古代中国の殷(商)王朝時代に使われていた最古の漢字です。今から3400年以上前の事です。 亀の甲羅(腹甲)や牛や鹿の骨(肩胛骨)に刻まれているので甲骨文字といいます。 その字は一見絵文字の様ですが、抽象性もすでに高く、文字の範疇にはいります。 殷の時代には、甲骨を占いに使いました。皇帝が政治のことや收穫のことを神にお伺いするのですが、そのお問い合わせをするのが占い師です。その占いグッズが甲骨。甲羅や骨などの裏側に小さな穴を穿ち、熱した金属棒を穴に差し込みます。そうしてしばらくおいておくと表側に卜形のひび割れが生じます。その割れ目の形で結果が判断されます。占い師はその結果を皇帝には直接伝えず(畏れ多くて直接には謁見できませんから)、その甲骨に文字で刻み付けました。それが甲骨文字です。文字は神と皇帝をつなぐものですから神聖なものでした。 金石文というのは、金属(主に青銅器)に鋳込まれた文字と石に彫り込まれた文字のことです。紙が発明される以前には文字は甲骨や金属、石に記録されていたのです。甲骨文字より後の時代の文字ですが、これも紀元前に生じた文字です。まだ文字を書く目的が、手紙のように遠方に思いを伝えるわけではなかったから、少々重い物に書写しても不都合ではなかったのでしょう。 これらの文字が、研究の対象、あるいは書としての作品制作、鑑賞の対象になるのはずっと後のことです。 金石文はかなり古くから研究が進んでいましたが、甲骨文が発見・研究されるようになったのは19世紀末のことです。 1899年、当時の清の国子監祭酒であった王懿栄は、持病のマラリアの治療薬として、竜骨と呼ばれていた骨を薬剤店から購入していました。その骨に何か文字が書いてあることを発見。「これは大発見!」と、薬剤店から竜骨を大量に買い集め研究を始めたというのがよく言われる逸話です。この逸話が真実か否かは不明であるが、研究が始まったのが1899年の前後であること、その先駆者も王懿栄であることには変りありません。 その後、甲骨を買い集める人が増えたのに目をつけて、何も書いていない骨に文字を刻み付けて売ることが多くあったと言われます。甲骨が出土していたのは殷墟(河南省安陽市の近郊、小屯村の近く)です、薬になるというので農民により発掘されていましたが、価値を知らない農民は文字の書いてあるものは傷ものと思ったのでしょうか、大部分を捨ててしまっていたということです。あー、もったいない・・・ |